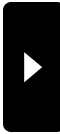2020年04月17日
子どものやる気を引き出す声掛けを 2
今回はやる気を引き出すほめ方についてです。
書き取りなら、きれいにかけている字や、今まで間違えたり書けなかったりした字が書けるようになっていたら、そこをピンポイントでほめます。
1ページに1つだけでも大丈夫です。
全体的に雑・・・褒めるところがない!と思っても、例えばこの字のこのはね方がいいとか、バランスがいいとか、どこか1つだけでも見つけてほめてみてください。
褒め方についてですが、大げさにしないことが意外と大切です。
「すごーい!!」とほめるより、淡々と「この字のここがいいね。」と伝えた方が、すんなり受け取ってくれます。書き取りが苦手(というより嫌い?)な娘も、1つ字をほめるだけで「この字(ほめた字とは別の字)はあんまり上手じゃないからもう一回書き直そうかな。」とすすんでやり直すこともあります。
算数など他の教科についても、前回できなかったところができるようになったところを見つけてほめます。
ほめるというよりは、認める、という感じでしょうか。
「この前はここできなかったのに、できるようになったね。」という風に。
私だけがほめるのではなく、家族に伝えてほめてもらうこともあります。母親だけではなく、父親やきょうだいからほめてもらうのも、普段とは違って嬉しいようです。
これが一番難しいことかなと思いますが、ほめるためにはお子さんをよく見ることが重要です。
何が苦手なのか、何をがんばっているのか、普段の子どもの様子はどうなのか。
昨日までとは違う何か、毎日頑張っている何か、その日特に頑張っている何かなど、小さなこと、ささいなことでもいいので見つけられると、認めやすく、ほめやすくなります。
ほめるのが苦手な方は、つぶやくだけでも大丈夫です。意外と子どもは聞いていますよ。
書き取りなら、きれいにかけている字や、今まで間違えたり書けなかったりした字が書けるようになっていたら、そこをピンポイントでほめます。
1ページに1つだけでも大丈夫です。
全体的に雑・・・褒めるところがない!と思っても、例えばこの字のこのはね方がいいとか、バランスがいいとか、どこか1つだけでも見つけてほめてみてください。
褒め方についてですが、大げさにしないことが意外と大切です。
「すごーい!!」とほめるより、淡々と「この字のここがいいね。」と伝えた方が、すんなり受け取ってくれます。書き取りが苦手(というより嫌い?)な娘も、1つ字をほめるだけで「この字(ほめた字とは別の字)はあんまり上手じゃないからもう一回書き直そうかな。」とすすんでやり直すこともあります。
算数など他の教科についても、前回できなかったところができるようになったところを見つけてほめます。
ほめるというよりは、認める、という感じでしょうか。
「この前はここできなかったのに、できるようになったね。」という風に。
私だけがほめるのではなく、家族に伝えてほめてもらうこともあります。母親だけではなく、父親やきょうだいからほめてもらうのも、普段とは違って嬉しいようです。
これが一番難しいことかなと思いますが、ほめるためにはお子さんをよく見ることが重要です。
何が苦手なのか、何をがんばっているのか、普段の子どもの様子はどうなのか。
昨日までとは違う何か、毎日頑張っている何か、その日特に頑張っている何かなど、小さなこと、ささいなことでもいいので見つけられると、認めやすく、ほめやすくなります。
ほめるのが苦手な方は、つぶやくだけでも大丈夫です。意外と子どもは聞いていますよ。

2020年04月16日
子どものやる気を引き出す声掛けを
宿題になかなか取り組まない、やり始めてもすぐに集中が切れてしまう・・・
そんなお悩みはありませんか?
そんな方に、私が実践している方法をご紹介しますね。
まず、なかなか取り組まないときの声のかけ方です。
「今日は何の宿題が出たの?」と聞きます。
「書き取り」とか「計算ドリル」という答えが返ってきたら、もう少し突っ込んで話を聞いてみます。
「新しい漢字習ったの?へー、こんな字も書けるようになったんだねぇ。」「算数はもう〇〇を習ってるんだね。」
など、会話をしながら、徐々に勉強に向けて気持ちを作っていきます。
これで自分からやり始めたらOKですが、それでも始められなければ、宿題をランドセルから出してみます。疲れてしまっていると、それすらもハードルになってしまうことがあります。宿題の部分を開きます。内容を見て、普段のお子さんの様子から、ここなら、この量ならできそうという部分に目を向けます。
書き取りなら1行から(それも難しければ一単語、一文字でもいいです)、算数なら解きやすいもの1問からやってみます。
「じゃあ、まずここをやってみようか。」と声掛けします。「ここだけでいいから」と言ってしまうと、「他はやらなくていい」と受け取ってしまいかねないので、言わないようにしています。
少しずつやっていきながら、減っていくやっていない部分にも目を向けます。「あと3文字で1行終わるね。」「あと2行で1ページ終わるね。」などです。もしそれでも疲れてしまったら、途中で休憩をはさみます。真剣に遊び始めてしまうと学習に戻ってくるのが大変なので、学校であったことを聞いてみるとか、少し体を伸ばしてみるとか、おやつを食べるとか、少しの時間でできることをしています。
様子を見て声をかけ、宿題に戻ります。
ポイントは「~しなさい」と言わないことと、「取り組みやすい声掛け・環境づくり」です。
お子さんに合う声掛けの仕方を探してみてくださいね。
そんなお悩みはありませんか?
そんな方に、私が実践している方法をご紹介しますね。
まず、なかなか取り組まないときの声のかけ方です。
「今日は何の宿題が出たの?」と聞きます。
「書き取り」とか「計算ドリル」という答えが返ってきたら、もう少し突っ込んで話を聞いてみます。
「新しい漢字習ったの?へー、こんな字も書けるようになったんだねぇ。」「算数はもう〇〇を習ってるんだね。」
など、会話をしながら、徐々に勉強に向けて気持ちを作っていきます。
これで自分からやり始めたらOKですが、それでも始められなければ、宿題をランドセルから出してみます。疲れてしまっていると、それすらもハードルになってしまうことがあります。宿題の部分を開きます。内容を見て、普段のお子さんの様子から、ここなら、この量ならできそうという部分に目を向けます。
書き取りなら1行から(それも難しければ一単語、一文字でもいいです)、算数なら解きやすいもの1問からやってみます。
「じゃあ、まずここをやってみようか。」と声掛けします。「ここだけでいいから」と言ってしまうと、「他はやらなくていい」と受け取ってしまいかねないので、言わないようにしています。
少しずつやっていきながら、減っていくやっていない部分にも目を向けます。「あと3文字で1行終わるね。」「あと2行で1ページ終わるね。」などです。もしそれでも疲れてしまったら、途中で休憩をはさみます。真剣に遊び始めてしまうと学習に戻ってくるのが大変なので、学校であったことを聞いてみるとか、少し体を伸ばしてみるとか、おやつを食べるとか、少しの時間でできることをしています。
様子を見て声をかけ、宿題に戻ります。
ポイントは「~しなさい」と言わないことと、「取り組みやすい声掛け・環境づくり」です。

お子さんに合う声掛けの仕方を探してみてくださいね。
2020年03月19日
こどもたちへ、テストを作りました。
3月頭に急遽学校が休みになったこどもたち。
受けるはずだった漢字大会、計算大会もなくなってしまったので、自作プリントを作ってみました。
上の子は漢字が得意なのでまんべんなく、下の子は苦手な漢字を中心に。下の子はカタカナもいまいちなので、カタカナプリントも作りました。
計算はいろんな問題を。
テスト開催は明日です!さぁて、どれくらいできるかな?

受けるはずだった漢字大会、計算大会もなくなってしまったので、自作プリントを作ってみました。
上の子は漢字が得意なのでまんべんなく、下の子は苦手な漢字を中心に。下の子はカタカナもいまいちなので、カタカナプリントも作りました。
計算はいろんな問題を。
テスト開催は明日です!さぁて、どれくらいできるかな?

2019年12月19日
親は何でも知っていなきゃいけない、なんてことはない!
子どもを育てていると、必ず直面するのが
「なぜ?どうして?」
の問いに答えられなくて困る、ということ。
空はどうして青いのか。
宇宙の外はどうなっているのか。
そんな疑問から、
分数のわり算はどうしてひっくり返してかけるの?
のように、学校で習った記憶はあるけどうまく答えられない・・・というものまで様々です。
そんなとき、どうしていますか?
知識豊富でなんでも答えてあげられたらいいのかもしれませんが、難しいですよね。でも、それでいいと思います。「親は何でも知っている」と思ってもらわなくても大丈夫です。
一緒に調べてみたり、「どうしてだと思う?」と考えさせてみたり、授業内容で分からないことは学校の先生や分かる友だちに聞く(お子さんが自分で聞いてくる)という方法もあります。
疑問に共感し、分かったことを共有したり、お子さんが考えたことをや聞いて分かったことをじっくり聞いてあげることも学びにつながります。
世の中にはまだ解明されていなくて分かっていないこともたくさんあり、今は常識とされていることが覆ることもたくさんあります。
疑問について納得するだけではなくて、「どうしてかな」と考え続けることも大切ですよ。

「なぜ?どうして?」
の問いに答えられなくて困る、ということ。
空はどうして青いのか。
宇宙の外はどうなっているのか。
そんな疑問から、
分数のわり算はどうしてひっくり返してかけるの?
のように、学校で習った記憶はあるけどうまく答えられない・・・というものまで様々です。
そんなとき、どうしていますか?
知識豊富でなんでも答えてあげられたらいいのかもしれませんが、難しいですよね。でも、それでいいと思います。「親は何でも知っている」と思ってもらわなくても大丈夫です。
一緒に調べてみたり、「どうしてだと思う?」と考えさせてみたり、授業内容で分からないことは学校の先生や分かる友だちに聞く(お子さんが自分で聞いてくる)という方法もあります。
疑問に共感し、分かったことを共有したり、お子さんが考えたことをや聞いて分かったことをじっくり聞いてあげることも学びにつながります。
世の中にはまだ解明されていなくて分かっていないこともたくさんあり、今は常識とされていることが覆ることもたくさんあります。
疑問について納得するだけではなくて、「どうしてかな」と考え続けることも大切ですよ。

2019年12月08日
おうちまつりの準備を始めました。~5~
これでおうちまつりの準備編も最後になります。
今回は、ゲームなどについてです。
今年は、さかなつり、しゃてき、わなげ、おかしつりをしました。これは去年子どもたちがとても気に入ったため、同じものをしました。
さかなつりは、厚紙に魚の絵をはり、口元にクリップを付け、割りばしの先にひもを付けた磁石で釣る、という誰もが1度はしたことがあるアレです。魚の裏には点数が書いてあり、制限時間内に規定の点数を取れたら賞品がもらえます。
射的は、厚紙に絵が描いてあるものを、割りばしで作った輪ゴム鉄砲で倒すゲームです。割りばし鉄砲はノーマル、強力タイプ、2連射など数種類あり、好きなものを選べます。的の裏には点数が書いてあり、規定の点数を取れたら賞品がもらえます。
輪投げは、新聞紙で作った輪っかで、小さめのお菓子やガチャガチャのケースに入った券を取ります。ガチャガチャのケースの中には、「からあげ無料」「わなげもう一回」などの券が入っています。お菓子は、個包装のグミやラムネなど、子どもたちの好きなお菓子を用意しました。
おかしつりは、子どもたちが好きなお菓子をいろんな種類買ってきて、それを組み合わせてビニール袋に入れ、ビニールひもで口を縛り、横倒しにした段ボールの上部の穴からひもを出します。おかしつりは100円ですが、『夏休みをがんばってきた子どもたちへのごほうび』として、用意しているので、1袋ほぼ100円のものを詰めます。1人3回ずつできるように、6つ用意しました。

ゲームでは何ももらえないこともありますが、普段他のおまつりでは存分にできないものが何度も何度もできることが楽しいようで、子どもたちはとても気に入っています。
今回は、ゲームなどについてです。
今年は、さかなつり、しゃてき、わなげ、おかしつりをしました。これは去年子どもたちがとても気に入ったため、同じものをしました。
さかなつりは、厚紙に魚の絵をはり、口元にクリップを付け、割りばしの先にひもを付けた磁石で釣る、という誰もが1度はしたことがあるアレです。魚の裏には点数が書いてあり、制限時間内に規定の点数を取れたら賞品がもらえます。
射的は、厚紙に絵が描いてあるものを、割りばしで作った輪ゴム鉄砲で倒すゲームです。割りばし鉄砲はノーマル、強力タイプ、2連射など数種類あり、好きなものを選べます。的の裏には点数が書いてあり、規定の点数を取れたら賞品がもらえます。
輪投げは、新聞紙で作った輪っかで、小さめのお菓子やガチャガチャのケースに入った券を取ります。ガチャガチャのケースの中には、「からあげ無料」「わなげもう一回」などの券が入っています。お菓子は、個包装のグミやラムネなど、子どもたちの好きなお菓子を用意しました。
おかしつりは、子どもたちが好きなお菓子をいろんな種類買ってきて、それを組み合わせてビニール袋に入れ、ビニールひもで口を縛り、横倒しにした段ボールの上部の穴からひもを出します。おかしつりは100円ですが、『夏休みをがんばってきた子どもたちへのごほうび』として、用意しているので、1袋ほぼ100円のものを詰めます。1人3回ずつできるように、6つ用意しました。

ゲームでは何ももらえないこともありますが、普段他のおまつりでは存分にできないものが何度も何度もできることが楽しいようで、子どもたちはとても気に入っています。
2019年12月08日
おうちまつりの準備を始めました。~4~
かなり時間があいてしまいましたが、おうちまつりの準備についての続きを書いていきます。
おうちまつりは、負担に感じることのないように準備を簡単に、また価格も抑えて楽しむことをモットーにしています。
今日は、食べ物販売についてです。
今年は去年の経験から、たこやき、フランクフルト、フライドポテト、バナナチョコ、ジュース、からあげ を準備しました。
たこやき、フライドポテト、からあげは冷凍のものを揚げるだけ、フランクフルトはトースターで焼き、バナナチョコは、バナナを切ってチョコソースをかけ、その上からカラースプレーをかけて出来上がりです。
プラスチックパックではなく、紙コップに入れることで、かさばらず、子どもでも持ちやすく、価格も抑えられました。
今はプラスチック製品をなるべく使わないようにしようという動きもあるので、そういう点でもいいですね。

おうちまつりは、負担に感じることのないように準備を簡単に、また価格も抑えて楽しむことをモットーにしています。
今日は、食べ物販売についてです。
今年は去年の経験から、たこやき、フランクフルト、フライドポテト、バナナチョコ、ジュース、からあげ を準備しました。
たこやき、フライドポテト、からあげは冷凍のものを揚げるだけ、フランクフルトはトースターで焼き、バナナチョコは、バナナを切ってチョコソースをかけ、その上からカラースプレーをかけて出来上がりです。
プラスチックパックではなく、紙コップに入れることで、かさばらず、子どもでも持ちやすく、価格も抑えられました。
今はプラスチック製品をなるべく使わないようにしようという動きもあるので、そういう点でもいいですね。

2019年08月26日
おうちまつりを開催しました。
小学校の夏休みが最後となった昨日、おうちまつりを開催しました。
今年は子どもたちと一緒に準備をし、準備ができた10時半からスタート。
出店は
・たこやき ・フランクフルト ・フライドポテト ・バナナチョコ ・ジュース ・からあげ
・さかなつり ・しゃてき ・わなげ ・おかしつり ・販売
の11店。
去年とは価格も見直し、10円単位で買い物ができるようにしました。
50円は10円がいくつでしょう?の問いに答えらなれかった1年生の娘も、最終的に「50円と10円を組み合わせて100円を払う」ということがスムーズにできるようになっていたのにはびっくり&笑ってしまいました。


この夏は、特に息子の成長を感じました。こちらが何も言わなくても、すすんで「今日の課題」に取り組み、どんどん終わらせていく。「毎日の課題を終わらせたらおまつりけんゲット」で、かなりの額を稼ぎました。たまにだらだら過ごしてしまい、夜になってしまってもそこから奮起してがんばっていました。
おまつりけんのためとはいえ、すすんでやることをやっていく姿勢は素晴らしかったです。
娘はやっぱりね、という感じで、「めんどうだから」「つかれたから」と、あと1~2こで終わるのに!というところでクリアできず、おまつりけんがもらえない日が何日もありました。
でも、おまつりが終わった昨日、お手伝いをお願いしたら「おまつりけんもらえないけど、やるよ!」と笑顔で答えてくれた娘。そういうところは本当に素晴らしいよ。
夏休みに一生懸命貯めたおまつりけんをすべて使い果たし、それでもまだ買い足りない・遊び足りない気持ちで終わりを迎えたこどもたち。
これまでの経験や、その気持ちから、何かを学び取ってくれるといいなぁ。
息子はお金をかせぐことの大変さも身にしみてわかったようです。
こうして今年も無事おうちまつりは終了しました。
準備編がまだ途中のままになっているので、また後日UPします。
今年は子どもたちと一緒に準備をし、準備ができた10時半からスタート。
出店は
・たこやき ・フランクフルト ・フライドポテト ・バナナチョコ ・ジュース ・からあげ
・さかなつり ・しゃてき ・わなげ ・おかしつり ・販売
の11店。
去年とは価格も見直し、10円単位で買い物ができるようにしました。
50円は10円がいくつでしょう?の問いに答えらなれかった1年生の娘も、最終的に「50円と10円を組み合わせて100円を払う」ということがスムーズにできるようになっていたのにはびっくり&笑ってしまいました。


この夏は、特に息子の成長を感じました。こちらが何も言わなくても、すすんで「今日の課題」に取り組み、どんどん終わらせていく。「毎日の課題を終わらせたらおまつりけんゲット」で、かなりの額を稼ぎました。たまにだらだら過ごしてしまい、夜になってしまってもそこから奮起してがんばっていました。
おまつりけんのためとはいえ、すすんでやることをやっていく姿勢は素晴らしかったです。
娘はやっぱりね、という感じで、「めんどうだから」「つかれたから」と、あと1~2こで終わるのに!というところでクリアできず、おまつりけんがもらえない日が何日もありました。
でも、おまつりが終わった昨日、お手伝いをお願いしたら「おまつりけんもらえないけど、やるよ!」と笑顔で答えてくれた娘。そういうところは本当に素晴らしいよ。
夏休みに一生懸命貯めたおまつりけんをすべて使い果たし、それでもまだ買い足りない・遊び足りない気持ちで終わりを迎えたこどもたち。
これまでの経験や、その気持ちから、何かを学び取ってくれるといいなぁ。
息子はお金をかせぐことの大変さも身にしみてわかったようです。
こうして今年も無事おうちまつりは終了しました。
準備編がまだ途中のままになっているので、また後日UPします。
2019年07月16日
おうちまつりの準備を始めました。~2~
ちょっと間が開いてしまいました。今日はおうちまつりの要ともいえる、おまつり券についてです。
去年は100円券と50円券だけでしたが、今年はそれに加えて500円券と10円券も準備しました。
下の子が小学生になったので、少しだけお金に近い種類で買い物できるようにしました。

それともう一つ。去年とは変わった部分があります。
去年は初めておうちまつりをしたということもあり、事前に何を売るか、何のお店があるかはほとんど子どもには教えていませんでした。(前日に、お店の看板を子どもたちと作りました。おもちゃ屋さんの内容については当日まではヒミツでした。)
今年は2度目で、何があるのかはだいたい子どもたちも分かっているので、サプライズより、『計画性』を重視しました。
計画性については、次回書きます!
去年は100円券と50円券だけでしたが、今年はそれに加えて500円券と10円券も準備しました。
下の子が小学生になったので、少しだけお金に近い種類で買い物できるようにしました。

それともう一つ。去年とは変わった部分があります。
去年は初めておうちまつりをしたということもあり、事前に何を売るか、何のお店があるかはほとんど子どもには教えていませんでした。(前日に、お店の看板を子どもたちと作りました。おもちゃ屋さんの内容については当日まではヒミツでした。)
今年は2度目で、何があるのかはだいたい子どもたちも分かっているので、サプライズより、『計画性』を重視しました。
計画性については、次回書きます!
2017年07月01日
わらび餅で学習(笑)
夕飯の買い物をしてたら見つけたわらび餅。子どもたちが食べたい!というので、食後のデザートに。
小学校1年生の息子にパックに入ったそのまま数を数えさせてみると、『…わからない』。
じゃあ、どうやったら数えられるかなー?と聞いてみると、お皿に出したらわかるよ!と。
お皿に出してみました。

数える息子。途中でわからなくなりました(笑)
さて、じゃあどうしよう?と聞くと、まっすぐ並べたらわかるんじゃない?と。
並べてみました。

ようやく最後まで数えることができ、『24こ!』
そこで、もっと数が多かったら、数えてる途中でもし話しかけられたら、わからなくなっちゃうよね?どうやったら数えやすいかな?から、10このまとまりを作ってみました。

『10、20、1.2.3.4…24こ!』と数えていました。全部を1から数えなくても全部の数が分かると納得できたようです。
「勉強を教えよう」としなくても、ちょっとしたきっかけから学んでいけたらいいと思います(^^)
小学校1年生の息子にパックに入ったそのまま数を数えさせてみると、『…わからない』。
じゃあ、どうやったら数えられるかなー?と聞いてみると、お皿に出したらわかるよ!と。
お皿に出してみました。

数える息子。途中でわからなくなりました(笑)
さて、じゃあどうしよう?と聞くと、まっすぐ並べたらわかるんじゃない?と。
並べてみました。

ようやく最後まで数えることができ、『24こ!』
そこで、もっと数が多かったら、数えてる途中でもし話しかけられたら、わからなくなっちゃうよね?どうやったら数えやすいかな?から、10このまとまりを作ってみました。

『10、20、1.2.3.4…24こ!』と数えていました。全部を1から数えなくても全部の数が分かると納得できたようです。
「勉強を教えよう」としなくても、ちょっとしたきっかけから学んでいけたらいいと思います(^^)
2017年05月29日
サンリオピューロランドに行って来ました。

娘が大好きなキティに会いに、ピューロランドに行って来ました。
とても混んでいてアトラクションの待ち時間は長かったけれど、ショーも見られたし、アトラクションも気に入ったようで息子も楽しめたようです
ある程度の年齢になってから、テーマパークに行く時はお小遣いを渡しています。
今回のお小遣いは1人1500円。
1年生の上の子には1000円札と500円玉で。年中の下の子には全部100円玉で。
持っているお金で何が買えて、どれくらいのお釣りが来るのかなど、いろんなことを学んで欲しいと思いそうしています。
上の子は自販機のジュースを買うときに「これって(500円玉)1枚で買えるの?」と聞いて来ました。500円は100円5個分だよ、と話しました。
下の子は、1500円の光るステッキが欲しかったようですが、それを買うと他に何も買えなくなるから別のにする!と自分で決めていました(普段なら買ってもらえないとぐずることが多いのですが)。
お小遣いの範囲内で、それぞれジュースを買い、上の子はアイスとお土産を一つ。下の子はお土産を二つ買いました。
それぞれに何か学ぶところがあったようです。
閉園まできっちり遊んで、「また行きたいね!」と話しながら帰って来ました。
楽しかったようでなによりです✨